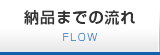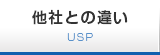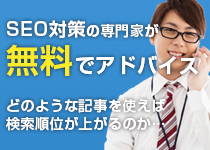SEO対策、記事作成に役立つ情報 一覧
記事文章の作成が進まなくなった時の対処法
記事作成に息抜きはNG!? 息抜きを挟むと記事作成がはかどるようになるのは、実は間違い。文章執筆スランプの多くは、休憩の取り方に問題があるのだと私は考えます。 以下、私の経験則で話をさせていただきます。 文章執筆スランプを招く間違った息抜き法記事作成の途中で、休憩だといってTVを観たり、ネットサーフィンを始めたまま、
公序良俗に反する記事文章ってどんなの?
記事作成は公序良俗を守る!検索から削除されないために 記事は、他の人が見て気分を害する内容にしてはいけません。もし書いた文章やアップした画像、動画が公序良俗に反するものであり違法性が高いものであれば、googleの検索から削除されてしまいます。 では、どのような内容が公序良俗に反するのか? 自分の記事は大丈夫なのか不安な人は、以下を参考に
文章を要約する3つのコツ
記事を短くまとめる方法 要約文は、長い文から短い文にまとめるのが基本です。 キャッチコピーなんかも同じです。一旦短い文で書いてから、短く削ったり、言葉を変えてまとめます。長文の要約も、それと同じなんですよね。 WEB記事での要約文の役割WEBサイト記事における要約文とは、検索結果に表示されるディスクリプションのことで
記事文章作成後の見直し手順
記事は推敲することで「質」が上がる 文章をどんなに綺麗にまとめたつもりでも、後に読み返してみると繋がりが悪かったり、誤字・脱字が見つかったりする箇所が大抵見つかります。試しに書いた記事を一日寝かして、次の日読んでみてください。 違和感のある箇所が意外に多く見つかるのではないでしょうか? 記事の推敲(見直し)のポイント
「推量」ばかりで文章を締めない
推量文の使い方と注意点 記事の作成において、「~かもしれない」や「多分~だ」などの推量表現を多用するのは、できるだけ避けた方がいいです。推量表現は、程よく使うのであれば大変便利ですが、根拠の説明をすっ飛ばす使い方をすると、文章の説得力がかなり薄れてしまいます。 例文を挙げますので、どんな感じになるのか?また、断定文との違いについて説明しま
文章における「助詞」の役割
記事文章作成における助詞の正しい使い方とは? ここでは、文章作成の前に知っておきたい、助詞の正しい使い方を説明します。 助詞のことについてネットなどで調べてみると、"品詞の一種であり、付属語の中でも活用の無いもの"とあります。文章を組み立てる上で、助詞にはどういった役割があり、また"活用"とはどういう意味なのでしょうか?ここで、詳しく解説
記事を読みやすくする接続詞の使い方
あまり知られていない?文章の接続詞の使い方 前後の文章同士は、接続詞を使って話の繋げます。 接続詞には色んな種類があり、「だから」のような順接、「しかし」のような逆接、対等関係をあらわす「また(並列)」や物事を付け加える「さらに(累加)」など、使い道が様々。これらは、各文章をつないで、話の流れをスムーズにしてくれるのですが、むやみに使いす
記事文章のカタカナ乱用は控える
文章はカタカナ表現ばかりだと読み難い!? 難しい漢字はひらがなに、専門用語は分かりやすく簡単に―――。記事を作成する時には、読む人がいるということを意識して、内容が伝わりやすい文章を書きます。 表現のために、漢字で書く語句をわざとカタカナで書くことがありますが、それ以外では、カタカナはできるだけ控えた方がいいんですよ。カタカナをみだらに多
記事文章は正しい日本語で作成する
日本語の正しい書き方を知っていますか? 記事でよくみかける間違った日本語の書き方について―――。 普段あなたが何気なく話したり書いたりしている言葉の中に、日本語の間違いが潜んでいるかもしれません。正しく日本語を活用している人から見ると、間違った日本語がところどころ混ざっている記事は、稚拙な印象を与えてしまいます。 特に、「ら」抜
文章を締める時のコツ
記事の結論は、読む人を意識して書きます。 読む人が情報を混乱させないようにするのが、解説文の結論の付け方―――。読む人を混乱させるのが、物語の結論の付け方―――。 記事の「結論」が持つ役割とは? 記事の結論の書き方は、文章のタイプによって変わります。 例えば解説文の場合―――。 結論には散らかった議論を1本
文字数が少ない記事文章と多いものの「書き方の違い」は?
文字数に応じた記事の書き方 依頼を受けて記事を作成する場合、文字数が定められていることが多いです。文字数が少ない物だと500~800文字程度、多い物だと1000~3000文字。 記事の文字数が少ない場合と多い場合では、少しだけ文章のまとめ方が変わるので、記事の文字数に応じた文章の書き方について説明したいと思います。
記事文章の「品質」と書く「スピード」の両方を維持する方法
記事作成で、品質とスピードの両方を維持するには? 記事作成には、書く内容のクオリティとスピードが要求されます。綺麗な文章が書けても完成までに時間が掛かりすぎるようでは厳しいですし、速いけれど記事内容が薄いのも良くありません。 品質とスピードの両方を維持しながら書くには、予め文章の「雛形」を作っておくと便利です。ここでは、簡単な文章構成例を
メリットを説明する時はデメリットの説明も
メリット記事の説得力を上げる方法 結構難しいのが、特定の商品やサービスのメリットを紹介することです。やりすぎると"やらせ"感が出てしまい逆効果に。ネット上に溢れている口コミ評判なども、偏った意見には信憑性が感じられないと思います。 そこで、ここではメリット記事を生かす方法について解説しました。 デメリットの説明がある
専門用語はひも解いてから使う
専門用語は簡単な言葉で表現を! 専門分野に関する記事を書く際に気を付けることは、「専門用語」の取り扱い方です。記事を閲覧する人の中には、知識を持っていない人もいるため、専門用語はそのまま使ってはいけません。 高度で難解な言葉は、簡単な言葉や文章にひも解いて読み手に伝わりやすくしましょう。ここでは、例として専門用語を取り上げ、簡単に説明して
見出し一つにつき主張は一つ
見出し内の主張のまとめ方 伝えたい事を文章に複数詰め込むと、読み手に内容が伝わり難くなります。また、安易に逆説文を挿入すると、意見が相反する二つの主張が並列するため、どっちつかずの文章になってしまいます そうならないよう、一つの見出しやセンテンスには、一つの主張についての内容だけを書くようにしましょう。 悪い例の見本として、例文
記事文章のネタの集め方
記事に書くネタの探し方 記事を書き始める時、意外に難航するのがネタ集めです。ネット上には、たくさんの情報が公開されていますが、テーマによっては、使えそうな情報が見つからないこともあるでしょう。 そのような時は、検索キーワードを変えて試してみてください。検索の仕方もコツがあるので、ここで説明したいと思います。 ネット検
句読点の上手な打ち方
句読点の打ち方ルールを知っていますか? 句点は文章の終わりに挿入する「。」の記号のこと。読点とは、文の途中、区切れに打たれている「、」のことです。正しく使うことで、長文でも伝わりやすい文章を表現することができます。 ただ、意外に多いのが、いらない箇所に句読点を打ってしまっているケース。 句読点には、打ち方にルールがあります。ここ
主語・述語の使い方を改善して読みやすく
主語と述語の使い方 読みやすい文章は、主語と述語の使い方が上手です。 主語はできるだけ短く表現したほうが、読みやすい文章になります。主語と述語の距離は、できるだけ近い方が伝わりやすいです。 ここでは、そんな主語と述語の使い方について解説していますので、参考にしてください。 長すぎる主語は短くする主語が一目で
知っておくと便利な文の基本「単文、重文、複文」
「単文、重文、複文」とは? 文章は、述語によって「単文、重文、複文」に分けられます。単文は、文中の述語が一つだけの文のことをいい、重文は、一つの文章に並列した主語と述語が二つ導入された文章です。複文については少々複雑で、「店員は心から謝罪したが、その客は許さなかった。」というように、一つの文に並列しない主語と述語のセットが2組ある文章のことをいいま
ターゲットを意識して書く
ターゲットを想定して記事を書く 記事を作成する時に意識しないといけないのは、読み手(ターゲット)です。まずは、本文を書き始める前に、ターゲットの想定を行ってください。 ターゲットによって、記事の方向性が決定します。方向性が決まると記事作成がはかどります。ここでは、それを踏まえてサイト記事のターゲット想定方法について解説しました。
文章内容の重複をチェック
文章の重複に注意しよう! 文章内容が、記事中の文章や他のページ記事の内容と重複する(かぶる)ケースがよく見かけられます。ここでは、どんなポイントで重複が起こりやすいかを説明していますので、記事作成の参考にしてください。 文章中の冒頭と結論の内容が重複する 【文章の冒頭と結論の内容が同じになってしまう】意外にやってしま
同じ言葉の繰り返し、接続詞の多用、二重否定を無くす
読みにくい文章表現を改善する 同じ言葉の繰り返し(重複表現)、接続詞の多用、二重否定文について、詳しく解説したいと思います。自分が書いた文章がどことなく変に感じたり、リズムが悪いのは、もしかするとこの3つの要素が当てはまっているからなのかもしれません。 間違った言葉の使い方は正しく直す。回りくどい表現はシンプルに。そうすることで、見違える
主語を削って読みやすい文章にする方法
文章を見直して練り直すことを推敲(すいこう)といいます。その際に主語の表現方法が長すぎて、読みにくいものになっていないか?をチェックすることが大事です。 主語の上手な削り方やまとめ方を説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。 余計な主語は削ってまとめてコンパクトに!詳しい文章を書こうとして情報をたくさん詰め込みすぎる
良質なコンテンツを作るために欠かせない具体的な文章の書き方
文章が「薄い」と、サイトに訪れたユーザーは読んでくれません。「だから何でだよ!」と思ってしまうような内容の記事は、WEB上にはたくさんあります。情報の少ない文は説得力に欠けるため、記事にはできるだけ具体的な情報を盛り込みながら、文章を展開していく必要があります。 では、具体的な文章とはどういうものでしょう?ここでその解説をしたいと思います。&nbs
WEB文章の基本形は、「リード・コンテンツ・締め」の三部構成
WEB文章の基本の構成を知ろう! ここでは、WEB文章で用いられる一番ポピュラーな文章構成を紹介したいと思います。 基本形を覚えておくことで、記事作成のスピードもアップするため、ぜひ参考にしてみてください。 「リード・コンテンツ・締め」が基本形WEB文章では、導入部である「リード部分」から始まり、「コンテンツの中核部分」、「ま
語尾をできるだけ同じ終わり方にしないコツ
語尾表現「敬体」と「常体」の使い方 文章の語尾表現には、「です。ます」調(敬体)と、「だ。である」調(常体)があります。 「だ。である」調の語尾は、文章が硬くなるので、親しみやすい印象がある「です。ます」調の方が好んでよく使われます。ですが、「です。ます」調の文章は、語尾が単調になることが多いようです。 文末が続けて「~です。~です。~です。」で終
文章完成後、一日置いて内容を見直すと・・・
作成した記事はどうやって見直せばいいのか? 作成した記事は、一度でもいいので見直してあげるとより完成度が高まります。 特に長文になればなるほど、修正前の状態では話のつながりがおかしくなっていることがあるので、そこを放っておかずにチェックして手直しすることで自己の文章スキルも上達しやすいです。 作成した記事はどんなに上出来に感じても、一度読
まずは構成から考える
記事作成は文章の構成から始める 文章も絵と同じで、ある程度の完成図がイメージできるように、下書きをした方がやりやすいと思います。 文章構成を書きながらやっていると、整合性の無いちぐはぐな文章になったり、要点がぼやけてしまうことが多いです。 まず最初に、書くテーマに応じた文章構成をおおまかでもいいので、考えてから本文を書き始めるといいでしょ
話題の膨らませ方
話題を膨らませてオリジナルの記事を作る方法 文章はテーマを深く掘り下げたり広げたりすることで、いくらでも話題を膨らませることができます。 そこで、ここでは一つのテーマから、それに関連する話を抽出して記事にする方法を紹介いたします。 ひとつのテーマから深まり、そして広がる話題 【切り口を変えて別の記事にする】 文章は、
長文でも読む気を失わせないコツ
長文記事を読みやすく変える「あるコツ」とは? 長文で文字が密集したような文章は、読む方の気持ちをくじけさせてしまいます。 そのため、書く側は、文章を見た目的にスッキリまとめる工夫が必要です。 ここでは、その方法を説明したいと思います。 長文を読ませる工夫 【読点までの文一節を適度に短く区切る】一文が極端に長いと、読み
興味を引くタイトルの付け方
タイトル名はWEB記事の中で一番重要! ここでいう「タイトル」とは、ユーザーがネット検索を行った時、検索項目に表示されるタイトルのことです。 例えば、ダイエットで検索した時に、「食べながら痩せるダイエット!」や「ダイエットのことなら○○」といったようなタイトルが並んで表示されます。 検索ユーザーは、このタイトルとそのすぐ下にある要約文(デ
SEOではテーマに関するキーワードを適度に挿入する
WEB文章の関連キーワード挿入方法と、スパムに関する注意点 SEOを意識したWEBの記事文章には、関連キーワードを自然な感じで文中に挿入しながら作成することが大事です。 そうすることで、記事を投稿したWEBサイトが、googleなどの検索エンジンに認知してもらいやすくなります。 そこで、ここでは関連キーワード挿入の基礎知識をお伝えいたします。&nb
見出しを用いて読みやすくする
見出しを用いると記事文章にまとまりができ、読み手が内容を理解しやすくなります。 書き手側としても、見出しを作成すると記事文章の骨組みができるので、本文の書き出しがスムーズになるので、積極的に導入してみてください。 見出しを使って一目で分かる記事を見出しには、本文に書かれている内容を読み手に対して一目で伝える効果があります。例えば、新聞に
箇条書きを用いて読みやすくする
箇条書きを用いると、長い文章も読みやすく仕上がります。 読み手に要点が伝わりやすく、記事文章を書く側も長文を繋げる必要がないため、非常に書きやすい方法だといえます。 では、どのように導入するのか?ここでは箇条書きの使い方について説明いたします。 要点を箇条書きで分ける長い解説文を一本調子で書いてしまうと、結局何が言いたいのかが伝わりにく