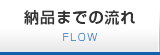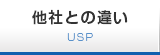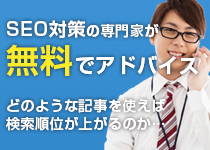文章における「助詞」の役割
記事文章作成における助詞の正しい使い方とは?
ここでは、文章作成の前に知っておきたい、助詞の正しい使い方を説明します。
助詞のことについてネットなどで調べてみると、”品詞の一種であり、付属語の中でも活用の無いもの”とあります。
文章を組み立てる上で、助詞にはどういった役割があり、また”活用”とはどういう意味なのでしょうか?ここで、詳しく解説したいと思います。
文章における助詞の役割とは?
助詞とは、単語にくっついて使われるもので、名詞や動詞、形容詞などを関連付ける働きがあるものです。
例えば、「私は記事を書いた」では、「は」と「を」が助詞です。
これらの助詞は、「私」と「記事」と「書いた」を関連づける役割を果たしています。
助詞があるおかげで、単語同士が意味を持ち、文章として成り立つのです。
つまり、助詞とは、「言葉」を繋げるための接着剤のような役割のある物だと認識していればいいでしょう。
助詞の”活用”とはどういう意味?助動詞との違いは?
活用とは、文に応じて語尾が変化することを指します。
動詞や形容詞、助動詞などは語尾が文に応じて変化するため、活用のある物といえます。
助詞には活用が無いため、単語そのものが変化しません。
【助詞と助動詞の違い】
助動詞は、動詞や体言(名詞)に意味を付ける役割を持っています。
助詞は、活用がありませんが、助動詞には活用があります。
活用があるというのは、語尾が文の意味に応じて変化することです。
受け身の語尾である「れる」「られる」や、「せる」「させる」などの能動的な語尾、「~だ」「~である」のような断定など。
ちょっとややこしいかもしれませんが、文章を繋げるために言葉が変化する助詞だと認識するといいでしょう。
助詞の「が」と「は」の違い
文章は、助詞を変えると全く違った意味になります。
ちょっと分かりにくいので、例文で見てみましょう。
例)
“私は買い置きしてあるプリンを食べた。”
この場合と
“私が買い置きしてあるプリンを食べた。”
この2つの何が違うのか?
前者は、「私」という人物がプリンを食べたという事実をただ言っているだけ。
いわば記録のようなものです。
一方、「私が」と書いた場合、「私」という存在が特定されています。
「私」がプリンを食べたということを、第三者に伝えている意味合いにとれるでしょう。
“私は山田 太郎です。”
“私が山田 太郎です。”
この2つの文も微妙に意味が変わってきますね。
前者は、ただの自己紹介なのに対して、後者は名乗り出ているような雰囲気を感じ取れるでしょう。
このように、助詞が違うと文章の意味が変わってしまいます。