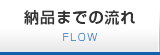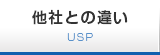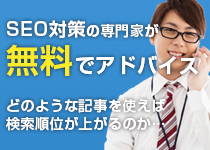専門用語はひも解いてから使う
専門用語は簡単な言葉で表現を!
専門分野に関する記事を書く際に気を付けることは、「専門用語」の取り扱い方です。
記事を閲覧する人の中には、知識を持っていない人もいるため、専門用語はそのまま使ってはいけません。
高度で難解な言葉は、簡単な言葉や文章にひも解いて読み手に伝わりやすくしましょう。
ここでは、例として専門用語を取り上げ、簡単に説明してみたいと思います。
専門用語の扱い方
基本的に記事に書く文章は、誰が読んでも分かる内容を目指した方がいいと思います。
専門性の高い内容がテーマだとしても、分かりやすく書くことに越したことはありません。
ビギナーには分かりにくい専門用語を、小学生でも理解できるような内容で説明することができれば、それだけで一つのコンテンツとして成立するでしょう。
やり方としては、専門用語を簡単な言葉で表現する方法があります。
【簡単な言葉に代える】
医療系には専門用語が多いです。
病名やお薬の名前など、一般的に知られている物も正式名称に変えると誰もその名称を知らなかったりします。
例えば、双極性障害という病名をご存じでしょうか?
これは、躁うつ病の正式な名称です。
また、医薬品では「シルデナフィル」。
これは、ED治療薬で使われているバイアグラの別名です。
詳しい人なら専門用語でも分かるかもしれませんが、知らない人は説明が無いと「どんな病気なんだろ?どんな薬なんだろ?」と、疑問を感じながら文章を読まなくてはなりません。
こういった名称は、世間でよく知られている名称の方を選択した方が、記事の内容が伝わりやすくなるでしょう。
【記事キーワードに専門用語が指定されている場合】
記事作成の案件によっては、記事ごとに指定キーワードの挿入が要求されることがあります。
そんなケースでは、専門用語に注釈をつけて説明をするのもアリです。
例)
双極性障害の治療には、~
(※双極性障害……躁うつ病のこと)。
例)
“アメリカで先日発表された非農業部門雇用者数は、前回の数値よりも……
(※非農業部門雇用者数……農業以外の業種で雇用された人の数)。
注釈は、文章の流れを邪魔しない便利な方法です。
専門用語には、こうやって注釈を入れれば後の文章で専門用語を使っても、読み手が内容を理解できます。
さらに、設定キーワードの問題も解決できるでしょう。
専門用語はターゲットを意識して、簡単な言葉との使い分けが大事
記事に載せる言葉は、ターゲットを意識して使い分けてください。
記事の読者ターゲットが専門家や専門的な知識を持った人の場合、専門用語を簡単な言葉に言い換える必要はありません。
専門用語を理解している人が読んでいるのに、いちいち説明することで、かえって回りくどくなってしまいます。
大事なことは、”どんな立場の人があなたの記事を読んでいるのか?”をイメージすることです。
依頼をもらって記事を作成する場合や自分のブログやホームページに文章を書く場合など、文章を書く動機は様々ですが、専門用語をケースバイケースで上手に使い分けて表現しましょう。