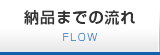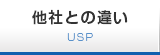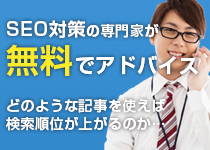「推量」ばかりで文章を締めない
推量文の使い方と注意点
記事の作成において、「~かもしれない」や「多分~だ」などの推量表現を多用するのは、できるだけ避けた方がいいです。
推量表現は、程よく使うのであれば大変便利ですが、根拠の説明をすっ飛ばす使い方をすると、文章の説得力がかなり薄れてしまいます。
例文を挙げますので、どんな感じになるのか?また、断定文との違いについて説明しましたので、参考にしてください。
推量文と断定文の違い
推量文と推定分、双方の違いを例文で見てみましょう。
推量文は、「~だろう」「恐らく~だ」のように、根拠や証拠が十分でない時に、書き手の考えで想像を述べるというもの。
例えば―――”○○の品種のリンゴは、皮が赤々と熟していて香りが強い。食べたことは無いが、恐らくどのリンゴよりも甘いだろう。”
そのリンゴが一番甘いかどうかはあくまで見た印象からであって、実際にリンゴを食べているわけではありません。
ただ、皮が赤く熟していて、リンゴの香りが強いから、果実も甘いと想像できるだろう、というものです。
一方、断定文は、「~だ」「~なのは間違いない」のように、ハッキリと言い切った文のことをあらわします。
“○○の品種のリンゴは、どのリンゴよりも甘い。”
リンゴが「甘い」と断定しました。
断定する時には、それなりの理由を添える必要があります。
詳しく突っ込んで書くなら、リンゴの糖度を他の品種のリンゴと比較して紹介したり、自分が食べてみた感想を具体的に述べるなど。
特にテーマが絡んでいる話の場合は、断定に対する説明が絶対に要ります。
○○の品種のリンゴが一番甘いかどうか?がテーマの記事であるのなら、筆者が「甘い」と断定した根拠を明確にしなければなりません。
他のリンゴをたくさん食べ比べて来た経験があるとか、リンゴ農家の人から直接話を聞いてきたとか……。
それが無ければ、読む人は、そのリンゴが甘いかどうかを信じることができません。
読み手が納得するような、リアルな説明が要るでしょう。
ただし、リンゴが甘いかどうかがその記事において重要でない話なのであれば、甘い!と断定したからといって、そこまで書きこまなくても大丈夫です。
テーマから話が逸れてしまいますからね。
そういう場合には、推量表現で十分ということになります。
薄い記事には説得力が無い!
記事テーマは、断定文で締めれるよう、根拠をしっかり調べることが大事だといえます。
記事の内容が推量ばかりだったり、断言していても根拠の説明が無い。
そんな記事を読んでも読み手は納得できません。
いわゆる”薄い記事”というものです。
“キャベツダイエットは、痩せると思います。だから試してみるといいでしょう。”
どうして痩せるのか?どんな人が試したらいいのか?がこの文章からは分かりません。
よって、キャベツダイエットが痩せるという話を、読む人が納得できませんね。
この場合、ハッキリ「痩せる!」と言い切り、その根拠を詳しく説明することが大事です。
読む人が「ああ、なるほど」と納得したら勝ちです。